新町松倉講第11回研修会 講演
〇 二見の古道と黒駒の渡し
講師 槇野 久春
ー 二見村古道の探求 ー
新町から黒駒(くろま)の渡しへの道と犬飼村への道について
第1章 はじめに
平成29年11月18日開催された新町松倉講の研修会(松倉祭り)にて、私は「新町堺筋から大沢越堺大坂道について」をまとめ発表した。これは「中家文書調査報告書」(五條市文化財調査報告書第13集)(五條市教育委員会編 平成26年3月31日発刊)の巻頭図版に掲載された宇智郡の俯瞰絵図(「馬借通路絵図」(江戸中期))に触発され始まった研究で、その絵図には新町筋から大澤寺を経て大澤越え(行者杉越え)の道が描かれていた。そこで古地図から現在住宅地図等までを比較し、また現地調査を踏まえて、新町から始まる「堺筋」とは堺へ通じる道であることを明らかにし、その役割や由緒について私見を交えて報告した。
今回は同じく「馬借通路絵図」に描かれた、二見村の二つの古道について探求したい。一つは新町筋西端から南に向かい、二見川端を抜けて黒駒の渡しにいたる道、もう一つは黒駒の渡しへの道の途中、御霊神社(二見宮山)の近くから二見村を西に向かい、犬飼村に至る道についてである。
令和元年11月16日第11回松倉祭りの研修会で『二見の古道と黒駒の渡し』の表題で発表する機会を得たが、この度は「黒駒の渡しについて」は別稿とさせていただき、「新町から黒駒の渡しへの道と犬飼村への道について ー二見村古道への探求ー」と題して二見村を通る二つの古道について説明をさせて戴く。
第2章 馬借通路絵図について
まず「馬借通路絵図」から検討したい。前回も触れたが、この絵図は江戸時代五條村の庄屋を務め、五條代官所御用達で掛屋でもあった中家が所蔵していたものである。絵図が描かれることになったのは、紀州橋本の馬借所と五條、須恵、新町村の馬借所との縄張りを巡る争いがきっかけとされている。その争いが訴訟に発展し、享保9年(1724)江戸の幕府評定所によって五條、須恵、新町村の訴えが裁可されるに至っているが、その際提出されたのがこの絵図と考えられており、従って絵図が描かれたのもこの頃、1720年代と推定されるのである。
絵図は訴訟の内容かr、紀州から和州に至る河南街道や阪合部村の通路が明瞭に描かれており、吉野川の南側が、北側に比し大きく重点的に描かれている。
この絵図において道筋は赤線で示されている。宇智郡の中心地であった須恵村、五條村、新町村を貫いて、東西に太く延びているのは伊勢街道である。馬借の道として、主要幹線道路として使用されていたことがよく伝わってくる。伊勢街道以外のの馬借の道はより細い赤線で描かれているが、これにも若干太さの違いがあり、馬借道路としての利用度、重要度を加味して描かれたと推察される。
新町村において、伊勢街道から発する道筋が二筋描かれている。一筋は前回報告した堺筋から大澤越えに至る道である。もう一筋は新町筋西端から南下し二見村を通る道である。後者の道筋が今回検討する黒駒の渡しへの道と、途中別れて西進し犬飼村へ至る道である。
第3章 黒駒の渡しへの道について
江戸時代中期、宇智郡五條村から吉野川を渡って南の野原・阪合部に至る道は、本馬借通路絵図で確認する限り、五條・野原間の橋(大川橋、野原柴橋?)を渡るか、黒駒の渡しを使う他に方策はなさそうである。通路絵図では二見村と黒駒村の道筋は、川に向かって繋がるように描かれており、その黒駒側の岸辺には一艘の舟が描かれている。五條・新町村から阪合部村へ、さらに河南街道を通じて紀州の富貴や恋野方面に物資を運ぶ時は、この黒駒の渡しを通る道が最も主要な通路であったと推察される。
この通路をよく見ると、新町から渡し場に向かって南下する際、途中3分の2程度を過ぎたところでクランク型に屈曲している様に見える。この屈曲の意味は「宇智郡二見村実測全図(明治22年4月)で詳しく説明するが、古道を探求する上で重要なヒントを与えてくれた。現在の道はここでクランクすることなく、直線的に川原に向かっており、江戸時代の古道とは明らかに異なるルートを辿っている。
第4章 「宇智郡二見村実測全図(明治22年4月測量)」(五條文化博物館蔵)について
本図は明治時時代に作られた地籍図であるが、新町村から黒駒の渡しまでの道筋が最も明瞭に描かれているので、この地図から先に説明したい。本図では伊勢街道が二見村の中央を貫く二重線で描かれており、その他の道筋は2種類の赤線で示されている。太い線が一等里道、より細い線が二等里道と区別され、黒駒の渡しへの道は一等里道として明瞭に示されている。因みに一等里道として記載されているのは他に新町中之町から北方面に発する堺筋のみで、この二つの里道が伊勢街道に次ぐ主要道路であったことが理解される。
さて、黒駒の渡しへの道は新町筋の西端、二見村との境から南に向かって発し、御霊神社近くで四つ辻にでる。この辻を東に向かえば、御霊神社の前を過ぎて二見城址に通じ、西に向かえば二見の大ムクノキに向かう道となる。道をさらに南下して二見の段丘崖を下ると、崖の直下で水路の北側を西に折れ、段丘崖に沿って雨師神社の湧水地に向かう。現在この段丘崖下の道は自生の竹藪に覆われ、ほぼ失われてしまったが、昭和39年4月の住宅地図でははっきり描かれており、現地に立ってみれば、最近まで使われていたと覚しき通路をほぼ見通すことが出来る。
その後一等里道は二見神社湧水地(あめっさん、雨主井戸湧水場)で南方へほぼ直角に曲がり、田畑の縁と水路の彎曲に沿い、ゆるやかに南下して吉野川の川原に至る。一等里道はそこをさらに突っ切って川岸までしっかり描かれている。
第5章 「二見村絵図」(五條文化博物館蔵 馬場文書)について
つぎに時代を少し過去に戻して「二見村絵図(江戸末期推定)」を見てみよう。この絵図は当時の土地利用図となっており、縮尺や形状はやや大雑把ではあるが、耕作地(田、畑)、水路、通路等が色分けされており、通路は赤線で辿ることができる。
さて、新町村から黒駒の渡しへの道をこの二見村絵図で確認したところ、御霊神社の西側を抜け南下した道は、二見城址に向かう四つ辻を越えて、さらにほぼ真っ直ぐ南に向かい、先程検討した明治22年の全図とは異なり、二見の段丘を下ってしばらく直進した後、田と畑の境界地で西方に屈曲している。その後二見神社湧水地のほぼ真南で南に折れて、黒駒の渡しに向かったと考えられる。この絵図にもクランクが有り、黒駒の渡しは雨師神社のほぼ真南に位置していたことに変わりないが、明治時代の「二見村実測全図」と較べて、クランチの最初の屈曲位置が若干南にずれていることになる。歴史的に見て「馬借通路絵図」はこの二見村絵図に近い道筋を通ったものと推定された。
どうしてこのような違いが起きたのか、地図を良く見比べると自ずと答えがでてくるように思われる。江戸時代の二見村絵図では、二見段丘下の水田の中央部に西流する水路が描かれている。渡し場への道はその水路周辺の湿地を避けるように、田と畑の境界部(おそらく吉野川の自然堤防で微高地となっていたのであろう)を通ったものと考えられる。ここからは私の推論であるが、その後、水田を整備するにあたり、水路を湧水の多い段丘崖直下に付け替え、二見(雨師)神社(湧水地)を経由して神社のほぼ真南にある渡し場へ向かう道が整備されたのであろう。またこのような整備の遠因として、御霊神社と二見(雨師)神社の間に密接な関係があったことが窺われる。現在でも両神社が一体となってお祭りが執り行われており、黒駒の渡しへの道は二見神社の真南に位置するのが本来の形であったと推定されるのである。
もう一点興味深いのは、二見村絵図において吉野川の川筋が時代とともに変化していることを示す証拠が残されていることで有る。この絵図では、吉野川の南、黒駒の渡しの阪合部側の川原に、二見村の村境が描かれているのである。洪水の影響で川道が北に移動しこのような絵図となったものと推察される。しかし、「宇智郡二見村実測全図(明治22年4月測量)」では現在と同様、吉野川の左岸(南側)に二見村の土地は描かれておらず、江戸時代末から明治にかけての僅かな期間に、このような状況は解消したものと思われる。
第6章 昭和から現在に至る黒駒の渡しへの道の変遷
明治33年式地図、昭和39年住宅地図、平成25年住宅地図((株)ゼンリン)等を参考にこの通路を確認したい。明治29年、二見村川端に当時国鉄の川端線が敷設されてより、この地域の景観は一変したものと思われる。川端線は二見駅で本線を離れ二見の段丘を南下し、水路により浸食された谷筋に沿い徐々に高度を下げ、二見段丘崖の中腹から陸橋を多用して優美な弧を描きつつ吉野川河畔に至っている。丁度黒駒の渡し近くに川端駅(当初二見駅)が設けられ、これ以降周辺には広大な貯木場が開設された。また明治45年には駅に隣接して索道(大和索道 川端ー富貴間)の基点が置かれ、木材や鉱物資源等の集散地となった。このため周辺に関連業者も多数あつまり、江戸時代以来の田畑や一等里道は寸断されてしまったようである。明治33年の地図で分かるように、新町から黒駒の渡しへの道は、二見から段丘を真っ直ぐ南下し、川場線を越えて川原に向かい、南西方向の渡し場に達している。
因みに二見段丘崖下の雨師神社に向かう道筋は昭和39年住宅地図にはしっかり描かれているものの、昭和62年版の住宅地図((株)ゼンリン)では道が一部消えており、地元の人々も次第に通らなくなったようである。
黒駒の渡しは昭和30年頃まで阪合部村への短絡路(ショートカット)として、住民にも広く利用されてきた。当時この渡し場を利用して阪合部と川端を行き来した人にお会いして話を聞くことが出来た。その詳細については、別稿の「黒駒の渡しについて」をご参照いただきたい。
平成6年4月に編集された「ふるさと旧跡と伝承(阪合部旧跡保存会)」によれば黒駒の渡しは昭和30年頃に廃止されたことになっている。しかし、最近の住宅地図(平成25年版(KKゼンリン))を見ても、県道を直線的に南下し、川原に出て南西方向、吉野川の岸辺に至る道筋が破線ではあるがはっきり描かれている。現在、この川原は砂利製造業者の資材置き場になっている。既に道は失われてしまったにもかかわらず、ここに道があったことを明示していることは非常に意義深い。住宅地図が過去の生活の痕跡をしっかり記録してくれていたことに感謝したい。
第7章 二見から犬飼への道について
次に江戸時代中期の「馬借通路絵図」に描かれた二見から犬飼への道筋について検討したい。「絵図」では、新町村から黒駒の渡しへ向かう道の三分の一付近から西に向かってほぼ直角にその道は発しており、二見村を抜けて少し波打つように、南西方向に向かい、犬飼村の真ん中を抜けて、伊勢街道へ通じている。黒駒の渡しへの道筋よりさらに細い赤線で描かれているが、これは馬借通路としての利用頻度或いは重要性が反映されたものと考えたい。
「二見村絵図(江戸末期)」の道と比較してみる。本絵図では二見村を抜けて犬飼村に向かう道は、二見御霊神社の南の四つ辻を右に折れる道が一筋描かれているのみである。北側を進む伊勢街道を除いて、二見の段丘上を西方に向かう道はこの道を置いて他にない。四つ辻を西に向かうと二見の大ムクノキの北側にいたる。この道は雨師神社から真北に向かう道と交差するが、そこは三叉路となっており、西へ真っ直ぐに向かう道は無く、水路に沿って南か北に進む他ない。「二見村絵図(江戸末期)」を見る限り、犬飼への道は左折して南に向かい二見(雨師)神社の西側から崖下に降りる道が、最短で最も妥当な通路と推察される。二見の段丘崖下には、「二見絵図」、「二見村実測全図」ともに水路に沿って東西にほぼ真っ直ぐ延びる道が赤線で描かれており、その道筋を西に向かうと二見村と犬飼村の境界付近で段丘上に上がり、犬飼村の中心部にでることが出来、これが馬借通路絵図に描かれた古道であったとしても矛盾しない。
一方、大ムクノキの先で右折して北に向かうとしたらどうだろう?水路に沿い北にしばらく歩けば伊勢街道に合流するが、「馬借通路絵図」の描き様に従えば、途中西に折れて大日寺を通り、犬飼へ向かう道を選択している様である。明治22年「二見村実測全図」に拠れば、大ムクノキから田圃を迂回して大日寺に向かうルートがありそうである。しかし、この道を辿ったとしても大日寺を通過した後、瓢箪池の堰手前で段丘の下に降りる道を選ぶ他なく、結局先程の崖下の道に繋がるのである。
二見村の中央を抜ける道筋のヒント
今回、現地調査中に地元の堀内伸晃(当時二見地区自治会連合会長)より重要な証言を得た。「二見のムクノキを西に過ぎ、三叉路を左折して南下、堀家の角(堀内家の東隣)には、私の子供の頃石の道標が立っていた。そこには手指のイラストがあり、左手は「伊勢」右手は「高野」とあった」と。それを聞いてこの道が昔の街道筋であったことを確信した次第である。その道標に従い、堀内家の前を西進し、さらに南下西進を繰り返して大日寺に抜ける道が、馬借通路絵図に描かれた道として最も矛盾がないと考えられた。江戸末期の「二見村絵図」には描かれていない道であるが、二見村で最も檀家の多かった大日寺の隆盛を思えば、その寺を通る道は馬借道として描かれたとしても不思議はない。道筋は寺を過ぎてまもなく段丘の下に降り、崖下の道を西に辿って、犬飼の段丘に上がるのは他のルートと全く同じである。昭和39年住宅地図を拡大し、ルートを赤く塗って馬借通路絵図と比較したが、この通路絵図の道と最もよく合致しているように見えた。
これにより「馬借通路絵図」の犬飼村への道には、二見村の段丘の上を通り抜ける道はなく、途中一旦段丘の下に降り、再び段丘崖を上がって犬飼村に至ることが判明した。すなわち、二見の段丘上を紀州に向かう道は、江戸時代伊勢街道を除いて存在しなかったと考えられるのである。
第8章 二見村から犬飼村への道の秘密
前章で述べた様に、二見村から犬飼村への馬借通路としては、馬借達にとって不利不便とも思われる段丘崖下を上下する道が描かれていると推定された。明治時代の「二見村実測全図」でも二見の段丘上で犬飼へ向かう道を探してみたが、明瞭に描かれていたのは崖下を東西に繋ぐ道のみである。瓢箪池の堰を抜け段丘上の道を辿ったとしても、烏が森堂付近の伊勢街道に抜ける道しか見当たらず、「馬借通路絵図」に描かれた犬飼村の真ん中を通る道とはなりえないのである。何故、犬飼村に向かう馬借通路が二見村の段丘上を進まず、十米余りの段差を伴う不便な道筋を選択していたのか、私なりその理由を考えてみた。
「二見村絵図(江戸末期)」を見て気づくことは、二見の段丘上では、6筋の水路がほぼ北から南に向かって平行に流れていることである。二見村は大規模な川成段丘にあり、赤線で描かれた道筋の、殆どがその水路に沿って南北に延びている、東西方向に向かう道は北側の山裾を行く伊勢街道を除いて、殆ど見られないのである。ことに瓢箪池の西方では東西方向の道は全く描かれていない、これはどういうことか。犬飼の古老に伺って気づいたことだが、最も西にある水路が段丘下に流れ落ちるところでは(現在犬飼の交差点付近)、浸食が激しく、以前は深い谷筋を形成していたとのこと。その谷筋で先祖が田圃を耕作していたという池田義美さんは『その谷は「サイタ谷」と呼ばれており、犬飼側は相当切り立った崖であった』と話してくれた。国道24号線や富貴に向かう県道(二見富貴線)が整備される時、その谷が埋められ、道路や土地が造成されたとのこと。今でこそ二見から犬飼へは、段丘涯の上縁に沿って通りやすくなったが、江戸時代はその谷筋を越えられず、大きく迂回を余儀なくされたのである。このため、一旦崖下に降り再度登ることは、手間はかかるが、崖下には東西に伸びる平坦な通路があり、余程通り易かったものと推量された。本道である伊勢街道が何故北側の山裾を遠回りしていたのか、以前より不思議に思っていたが、南北に走る水路とその谷筋を避ける意味があったのだと漸く合点できた、先人の知恵に納得した次第である。
段丘崖下から犬飼に上がる道は、江戸と明治の地図から見て、二見村と犬飼村の境界付近を段丘崖に沿い斜めに登る道であり、その後現在の県道二見富貴線に出たものと思われる。現在でも里道があり、川西儀一氏宅の北側にその里道は確認出来る。犬飼村近くのその道は現在でも里道として利用可能だが、川端の田園地帯が県営の下水処理場として買い上げられて以降、崖下に沿って伸びていた古道は殆どが失われ、現在通行することは不可能となってしまった。誠に残念である。
川西儀一氏やその母(故シゲノさん)のお話では、昭和の時代にはその道を通る人をよく見かけたとのこと。江戸時代や明治時代のみならず、ごく最近まで犬飼から二見、新町、五條に抜ける道としてこの道はよく使われていたのである。
第9章 犬飼村の古道について
段丘上に出た道はすぐ、犬飼から烏が森堂に向かう道を分岐して南に向かい、まもなく釈迦寺の手前で西に曲がり、犬飼寺の南西角で伊勢街道本道に合流している。犬飼村のこの道筋は古道と現在の道がほぼ一致している。
犬飼から烏が森堂に向かって分岐した古道はゆるゆると里道(明治八年改正犬飼村地引絵図にも明記、現在は拡張舗装されている)に沿って北西に向かい、国道及びJRの線路を越えて、烏が森堂で伊勢街道本道に繋がっている。『烏が森堂からは裏手の山道を登って花咲峠へ出る道があり、以前は木の原、大澤に向かう近道として犬飼の人たちがよく利用していた』とのこと、この道沿いに在住する坂口友章氏の話である。旧国鉄の軌道により分断されたこの道は犬飼の生活道であるとして、坂口氏の父、昇さんは国鉄に再三踏切設置を要望したが全く聞き入れられず、憤懣やるかたない思いを生涯持ち続けていたとのことである。この道は今も国道とJRにより寸断されたままであり、誠に遺憾としか言いようがない。
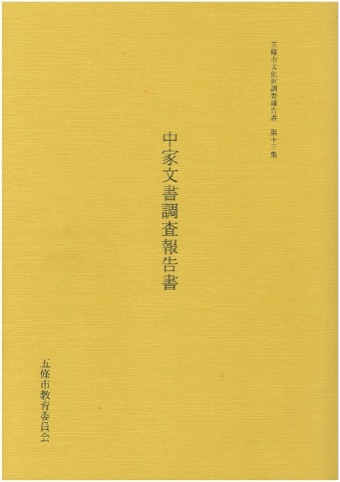
のコピー.jpg)



(明治22年「宇智郡二見村実測全図」 五條文化博物館蔵)
(明治22年二見村実測全図拡大)
「中家文書調査報告書」
(五條市文化財調査報告書第13集)
五條市教育委員会編 平成26年3月31日発刊
(中家文書調査報告書より馬借通路絵図 中家文書)
(馬借通路絵図 二見村、犬飼村拡大)

(「二見村絵図」(馬場文書、五條博物館蔵))

(明治33年式地図)

「ふるさと旧跡と伝承」(阪合部旧跡保存会)
平成6年4月編集



(堀内家長屋門)
(堀内家門前より大日寺に向かう古道)


(大日寺本堂北側の道)
(瓢箪池堰より県下水道処理場を望む)

(昭和39年住宅地図より二見地区通路を赤線で示す)


(瓢箪池崖下の水路東方面を写す)
(瓢箪池崖下の水路西方面を写す)


(江戸時代の二見村絵図に道赤線、水路青線を入れてみた)
(国道24号線犬飼交差点、
東南方向を写す)

(犬飼村から崖下の道への下り口)

(「明治八年改正堺懸下大和国宇智郡犬飼村地引繪図」川西儀一所蔵)

(二見御霊神社の近くの四つ辻
より西方を望む)
(二見の大ムクノキ付近の古道)