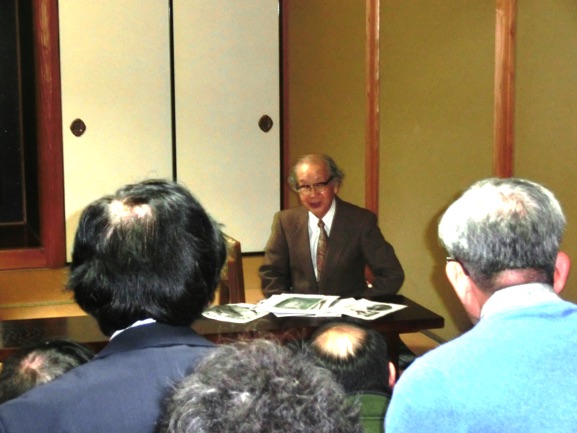第7回『松倉祭り』松倉豊後守重政公報恩法要と
新町松倉講 第7回例会・研修会
毎年は重政公の命日の11月に「松倉祭り」を行うのですが、今年は12月に本市に来られる島原文化財保護委員会会長・島原城資料館専門員である松尾卓次氏に講演をお願いしたため、1ヶ月後の12月に致しました。
2015年は大坂の陣400年記念の年で、今回も昨年同様大坂の陣で命を落とされたすべての将兵の御霊を慰霊する法要とする一方で、本市の元気なまちづくり交付金からの助成もあり、燈火会は盛大にそして研修会は二つの講演会が出来、大変充実した内容となりました。二つの講演会というのは、御一人は先に紹介いたしました松尾卓次氏で、もう一つの講演は、五條市立五條文化博物館館長の藤井正英氏によるものでした。
今回の「松倉祭り」は、午後4時から大坂の陣で戦死されたすべての将兵の御霊を慰霊する燈火会をはじめました。今年は特に新町通り約600mほどにわたって燈火を配置しました。
新町通り 燈火 西方寺 正門
午後4時30分からは、新町松倉講の第7回例会・研修会を西方寺客殿にて行いました。講の代表槇野久春氏の開会の挨拶のあと、来賓として来ていただきました五條市長太田好紀氏の御挨拶をいただきました。参加者は50名を超え、客殿の廊下まで椅子をだし、大変盛会でした。
このあと、講演に入りました。この講演について紹介したいと思います。
(講演)
「新資料から見た江戸時代新町住民の家族像」
五條市立五條文化博物館館長 藤井正英氏
昨年と今年2015年の両年に新町の江戸時代の庄屋をされていたお宅のふすまの下張りから多くの文書が発見されました。慶応年間の村々の年貢銀、五人組合帳、宗門改帳、反故紙の習字用紙などでした。今回の講演は、これらの新資料の文書から読み取れる江戸時代の新町住民の家族像についてでした。大変細かく文書を整理、分析されたものでしたが、以下、講演の簡単な概略のみを紹介させていただきます。
宗門改帳関連文書について
これは18世紀半ばから19世紀初頭の文書のようで、7〜8年分あり5ケ寺分である。宗門改帳の記載様式は、戸主とその家族、自分の持ち家・借家・かし屋などの区別、下男・下女(奉公人)を記載する、除籍の理由を記す、などである。
新町村の旦那寺(檀那寺とも書く、檀家寺のこと)は、現調査段階では5ケ寺が確認できる。ある文書から
は、46家の合計人数218人(下男・下女含)分が判明できた。46家の家族の様子、妻の出身村別や奉公人(下男・下女)の出身村の記載、また家族の変化・屋号についてなど、実に細かい一覧表にして説明をしていただきました。情報が多すぎてとても紹介できないのですが、ほんの少しを簡単に紹介します。
○ 46家合計人数218(下男・下女含)人。下男下女25人を除くと193人。それを平均すると
一家平均4.4人。
○ 妻の出身村別では、判明しているのは36例で、大和国内の宇智郡からは29例で80.6%、宇
智郡以外は7例で19.4%。
〇 奉公人(下男・下女)(28名)の出身村では、宇智郡内は19人(70.4%)、宇智郡外は2人、
紀州から6人(22.2%)、不明は1人である。奉公人の年齢は平均23.04歳と若い。
○ 家族の変化・屋号に関しては、男の改名はしばしば見られるが、女子の改名はほとんど見られないよ
うだ。
家族の変化に関しても細かくわかり、江戸時代のこの時期における新町に住んでいる人々の家族像が垣間見られて、大変興味深い講演でした。
(文責 来田)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
(講演)
「松倉氏の島原城・島原城下町築造400周年に向けて」
島原文化財保護委員会会長・島原城資料館専門員 松尾卓次氏
松尾氏は以下の2点に別けて話をしてくれました。
1 島原城・島原城下町築造400周年へ向けて取り組みたいこと
2 松倉重政・勝家の歴史的評価について
1 島原城・島原城下町築造400周年へ向けて取り組みたいこと
2016年 「松倉重政入封400年周年」〜松倉一族について
2018年 「島原城築城開始」〜天下の名城・島原城—県文化財指定に向けて
2018年 「島原城下町築造開始」〜有明海上交通の要地・島原湊
2019年 「松平忠房入封350周年」〜歴代島原藩主松平氏の治世
2021〜2025年 「島原城・島原城下町」〜島原のさらなる発展を求めて。
2 松倉重政・勝家の歴史的評価について
父 重政 島原城及び島原城下町築造の祖として評価したい。城築城の折領民を酷使したので
疲弊した領民が反乱を起こしたのが島原の乱だと説く人がいるが、そうは思わない。
島原城の築造を可能にしたのは、有馬氏時代からの豊かな財力があったから。有馬
氏は海外貿易により多くの収入を得ていた。また、領国の生産性向上のために、数
キロにわたる千々石(ちじわ)防風林の植栽、串山諏訪の池築堤や櫨(はぜ)の導
入と木蝋の生産の元を開いたといわれている
息子 勝家 海外貿易が禁止されて、藩財政を領国生産品に重点を置かざるを得なくなった。改
めて検知をして5万石(旧4万石)を打ち出さねばならず、おまけに寛永の大飢饉
の発生で収穫物の減少と、農民の負担増。また、有馬氏の延岡転封に随行しなかっ
た旧家臣の土着化した地侍・庄屋化した者の指導などが原因となった島原の乱が起
こった、と理解している。もちろん同様にキリシタン弾圧の激化もいうまでもない。
このように、両者の施策と時代背景の違いを明確にしておくことが必要。松倉氏の生産力の把握がズサンで、過酷な税が課されたことが多くの資料に見られるといわれるが、松倉氏が没落し、同時に多くの資料も失われたから、海外の教会側の資料に頼らねばならぬ点もあり、正確さを欠くところがある。
島原城は圧政のシンボルか
乱直前の重税とその厳しい取り立てはそのとおりでしょう。しかし、島原半島北部の農民は不参加だった。反乱する必要性がなかった。つまり、生産性の低い南部一帯の農民が追い詰められて一揆を起こす。それには元の地に残った有馬の残党(旧家臣)が庄屋化して農民を導いて反乱を引き起こしたことと関連する。それより以前、島原城落成時に城主松倉重政は領民を招いて、祝いの能楽を開いている。今でも松倉氏から城に一番近い屋敷を与えられて、「升屋」と屋号をつけた旧家も残っている。これらの人にとって島原城は「オドン(おら)が城」なのです。北目(北部)の人たちはこのように見ている。したがって、島原城は圧政のシンボルでは決してなく、自慢の島原城でもある。
松倉勝家の悪政のイメージで島原城を眺める人があるようです。あまりにも島原城に対する誤解がある。それは、たぶんに某歴史小説家(司馬遼太郎 注来田)の影響があるようだ。
もう数年で、島原城築城400年を迎える。島原城と島原城下町づくりの祖として松倉重政を改めて評価しなければならない。
(松尾氏のレジメより 文責 来田)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
多くの方が「松倉祭り」、燈火会・例会・研修会に参加してくださり、大変盛会のうちに第7回「松倉祭り」 を終えることができました。参加していただいた方々、どうもありがとうございました。